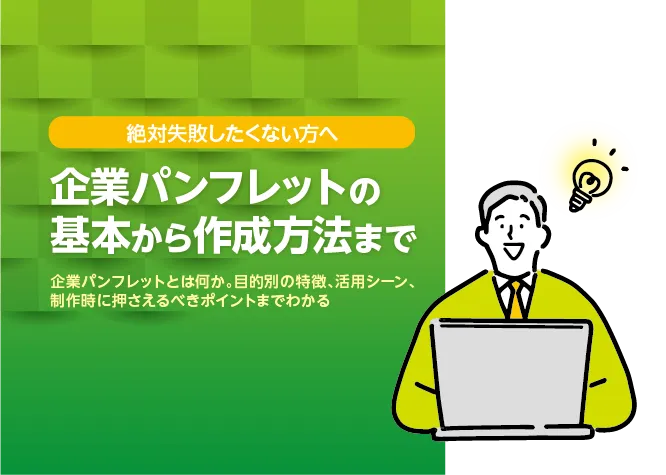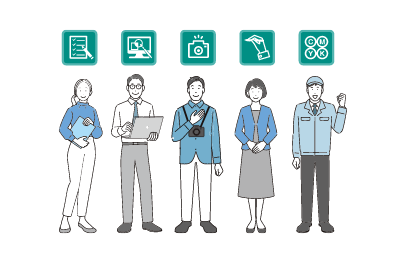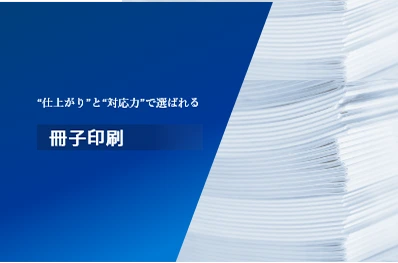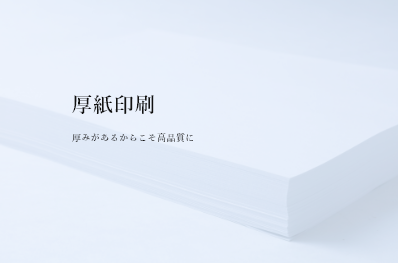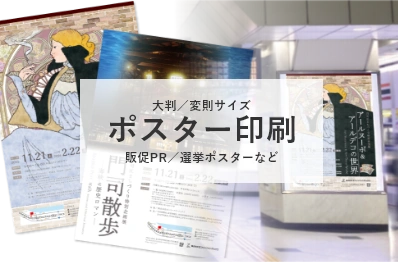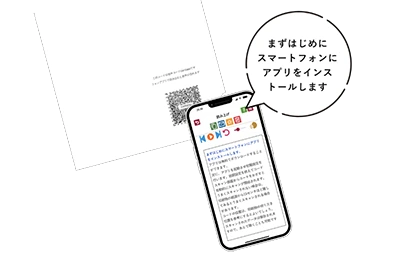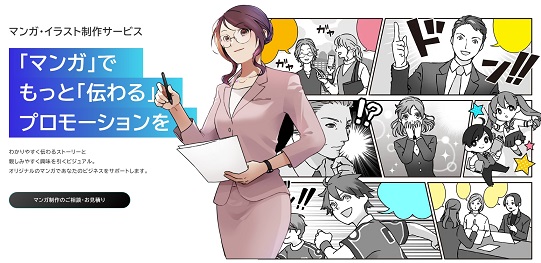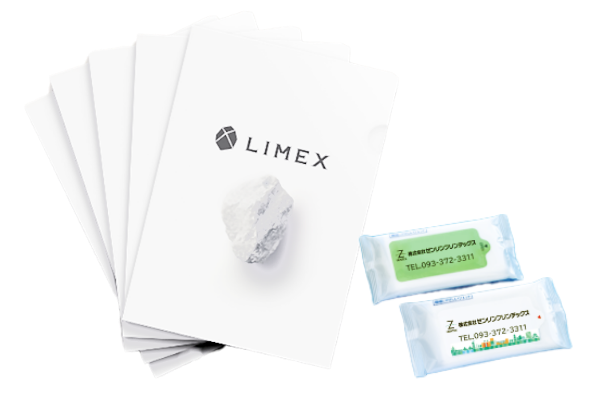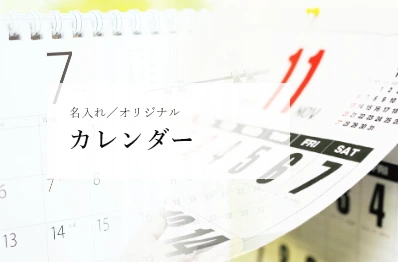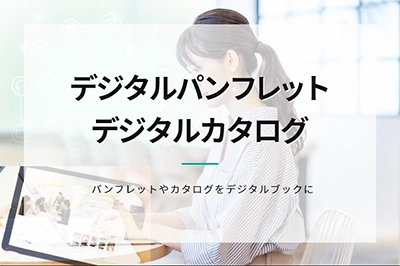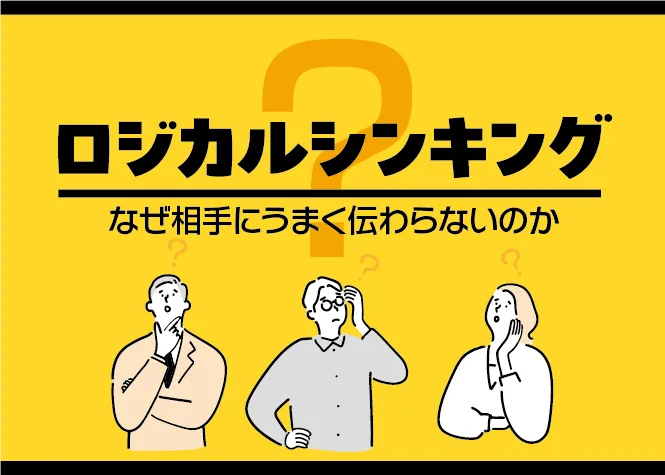

▼ロジカルシンキングの基本を知りたい方には、こちらの記事がおすすめです
・ ロジカルシンキングとはなにか-基本をわかりやすく説明
この記事では、ビジネスのコミュニケーションの場でロジカルに説明する方法をご紹介します。
ロジカルな説明とは
ロジカルな説明=わかりやすく伝える→納得してもらう→思い通りの反応を得る
ロジカルな説明とは、わかりやすく伝えて相手を納得させ、思い通りの反応を得ることです。
コミュニケーションにおいてロジカルシンキングを活用する目的は、顧客や取引先、上司や部下、同僚、消費者などに何かを伝える際に、相手を納得させて自分の思い通りの反応を得るためです。
そのためには、筋の通った論理的な説明で相手を説得する必要があります。
例えば、顧客に対して課題解決のプレゼンテーションを行う場合を考えてみましょう。
プレゼンテーションでは、顧客に自社の商品やサービスが必要だと感じてもらうことが望ましい反応です。
そのためには、
- 現状や課題解決方法などを一貫性のある方法で伝える
- 説明要素の過不足や伝えた情報から本当に結論が導かれるかに配慮しながらプレゼンテーションを組み立てる
- 相手にとって理解しやすくわかりやすい説明をする
という3つの配慮が必要です。
しかし、うまくいかないこともあるかもしれません。 場合によっては、
- 自分の言いたいことだけを伝えてしまう
- 相手の課題や反応を考慮しない
- 論理的なつながりや根拠が不明確
という状態になってしまっているかもしれません。

広告の作成においても「ロジカルに伝えること」は応用できます。例えば、インターネット広告のランディングページでは、ターゲットや商品を考慮した論理展開が重視されます。商品の素晴らしさだけを並べても消費者を説得することは難しいため、分かりやすい論理展開で納得感や共感、信頼、信用を得て顧客を次の行動に導くことが考えられています。
ロジカルに伝えるための基本とは
ロジカルに伝えるための基本として、おさえておきたい事が3つあります。
もしかすると、当たり前のように感じるかもしれませんが、意外と見落としがちなことでもあります。
自分の考えだけを伝えてしまう、自分しか分からないという事態に陥ってしまう…、
このような事にならないように、ぜひ確認しておきましょう。
1. 相手に伝えるべき課題を明らかにする
まずはじめに、プレゼンテーションや会議の場で「伝えなければならないこと」「答えなければならないこと」は何かを確認する必要があります。
例えば、顧客や消費者に自社サービスをおすすめする際に、相手がそれを課題と認識していない状態では、いくらサービスを説明しても、相手がそれを課題と認識していない場合は、商談は上手くいかないでしょう。
自社サービスの説明をする前に、顧客や消費者が置かれている状況(今どのような課題や問題があるか)、つまりそのサービスが必要な理由を共通認識として持ってもらう必要があります。
そのためには、相手に伝えるべき課題を明確にし、それを的確に伝えることが大切です。
伝えるべきことが途中で変わる?
ところで、「会議での報告のために課題に対して検討を進めていたが、あれやこれやと伝えたいことが増えてきた…」
こんな経験をしたことはありませんか。
その課題を解決するのについ熱心になるあまり伝えたいことが溢れて、いつの間にか頭の中で課題がすり替わったり、ずれたりするのはよくあることです。しかし本人も気が付かないうちにそのような状態になることは避けなければなりません。
では、もしそれが重要なことであった場合はどうでしょうか。
そのような時は、課題自体が変わったこと、またなぜ変えなければならないのかを受け手(説明を聞く人)に説明し、それがいま検討すべきことだと認識してもらわなければなりません。
受け手がテーマとして認識していなければ、きちんと伝わることは難しいのです。
2. 期待する相手の反応を明らかにしておく
プレゼンテーションや会議の目的の多くは、「伝えること」だけではないでしょう。
例えば、「理解してもらう」「判断/承認してもらう」「意見を聞く」「何か行動を起こしてもらう」など、何かしらの目的があるのではないでしょうか。
相手からどのような反応をひき出せば、目的を達成した(=成功)とするかを決めておくようにしましょう。
受け手が「だから、どうして欲しいの?」「結局、何が言いたいの?」という状態になることを防ぎます。
3. 「答え」に必要な要素を満たすようにする
課題に対する「答え」は、相手が理解し納得できるものにしなければなりません。
そのため説明には次のような要素を満たすようにしましょう。
明確な答え、得られる効果
課題の生じる原因、結論にいたる納得できる理由
原因を解消するための具体策
[参考]プレゼン資料の基本構成
プレゼンテーションの資料でよく用いられる構成を見てみましょう。
上記の内容を満たしていることが分かります。
| 1. 現状報告 | (1)何が課題なのか (2)課題が生じる原因は何か |
| 2.提案内容 | (1)解決策、改善案 (原因を解消するための答え) (2)効果予測 |
PREP法
その他にも、ロジカルなプレゼンテーションのために用いる手法にPREP法があります。
PERP法とは
はじめに結論・要点を伝え、結論にいたった理由、事例やデータの提示、最後にもう一度結論・要点を述べる方法。
- Point :結論・要点
- Reason :結論にいたった理由
- Example:事例やデータ
- Point :結論・要点
わかりにくい・説得力のない説明の特徴
「わかりやすく説得力のある説明」をするためには、「わかりにくく、説得力のない説明」について知ることも重要です。
ここでは、「わかりにくく、説得力のない説明」とはどのようなものか考えてみましょう。
1.話の内容に“ダブリ(重複)”がある
例えば、ある企業H社では、社内システムの一部を新たにクラウドサービスを利用すべきか検討しています。
担当者のMさんは、会議の場で、クラウドサービスを導入すべき理由を次のように説明しました。
- コスト削減
クラウドサービスを利用することで、新たなハードウェアの導入やメンテナンスにかかるコストを削減できます。
現状はサーバーを自社内で運用しており、ハードウェアの購入(更新)費用、専門スタッフの費用がかかっています。
しかし、クラウドサービスを利用することで、これらのコストを大幅に削減できます。 - 柔軟性と拡張性
クラウドサービスは柔軟性と拡張性があり、今後の変化に合わせてスケーリングでき、迅速かつ容易にリソースを追加することができます。もちろん変化に応じて不要なリソースの利用を停止することができます。
つまり必要なものを必要な時に必要なだけ使用することができるため、コスト最適化に繋がります。 - セキュリティとデータバックアップ
クラウドサービスは高度なセキュリティ対策を施しておりデータを保護します。例えば、データセンターでの24時間体制の監視やデータの暗号化、バックアップの自動化などがあります。
これにより、顧客はセキュリティリスクやデータの損失から守られ、安心してビジネスを展開できます。
以上の説明で、コスト削減と柔軟性・拡張性、セキュリティとデータバックアップの利点が述べられています。
しかし、1.コスト削減と2.柔軟性・拡張性の間には重複が存在し、また3.セキュリティとデータバックアップも一部コスト削減に関連している可能性があります。
このように内容に重複が見られると、受け手に「きちんと整理されておらず検討が足りないのではないか」といった疑念が生まれる可能性があります。より明確かつ整合性のある説明をするためには、重複した情報を排除し、各ポイントを独立した観点で説明することが重要です。
2.話の内容に“ヌケ(漏れ)”がある
説明の内容にヌケ(漏れ)がある場合も同様です。
明らかに説明に欠落した部分があるのにも関わらず、なぜその事に言及しないのかが分からないと、理解不足や信頼の低下といった様々な影響が生じることがあります。
それでは、ある学校法人が入学者を増やすための広報活動を考える場面を見てみましょう。
ある学校法人に勤めるAさんは、広報担当者として、新規入学者を増やすために隣の県の学生をターゲットにするという提案をしました。
Aさんの説明:
「当校は現在、県内の学生を主なターゲットとして入学募集を行っています。しかし、競合校Bが隣の県Cに広告を出しているという情報がありますので、広報活動のエリアを拡大し、隣県Cの学生もターゲットにするべきだと思います。」
あなたならこの説明を聞いてどのように感じますか?
もしかすると次のように感じたかのではないでしょうか。
- この学校の直近の入学者の傾向は(現状は)?
- なぜ競合校Bは、他の県ではなく隣県Cに進出しているのか?
- 隣県Cに関する情報は?最近発展しているの?
- 隣県Cの学生にアプローチするリスク、しない場合のデメリットは?
- 具体的な広報戦略は?
- 県内学生に対してはどうするのか、広報の内容を変更するのか?
など
このように、明らかに説明が不足していると、受け手は「容易に思いつくような事なのに、なぜ言及しないのか」と信憑性に疑問を抱いたり、不確実さを感じる可能性があります。
これらの疑問や関心事を明確に説明することで、受け手は提案の根拠や背後にある考え方をより理解しやすくなります。
また、不足していた情報を提供することによって、説明の信憑性や説得力を高めることができます。
説明を行う際には、自分自身が受け手の立場になって考え、情報の漏れや疑問点がないように注意しましょう。
それによって、わかりやすく説得力のある説明をすることができます。

▼話のダブリ(重複)やヌケ(漏れ)をなくすMECEについては、こちらの記事がおすすめです
・ MECEとは?|MECE(ミーシー)の具体例、フレームワークとの関係を解説
3.話が飛ぶ
まず、「話が飛ぶ」というのはどういう状態か確認します。
話が飛ぶとは、つながりや脈絡が不明確、もしくはそれを相手に伝えないため、話に一貫性や論理性が欠ける状態のことです。
では例を見てみましょう。
あるBtoB企業であるD社の営業部長Eさんは、今期の営業施策を課員に説明しました。
前期は思うような結果が残せなかったため、その課題を解決するための施策です。
しかし、それを聞いた営業担当の皆さんは首をかしげています。
〈施策1〉
- 前期の課題
主要顧客に対して訪問回数を増やしたが、売上が落ちた - 今期の施策
主要顧客に対してはさらに訪問を増やし、休眠顧客にはインサイドセールスでの対応を開始する

Fさん
前期は主要顧客への訪問回数を増やしたのにも関わらず売上が落ちた。
さらに訪問回数を増やしても意味がないのではないか?
前期の課題を踏まえているのか疑問だ。
また、取引が途絶えている顧客(休眠顧客)に対して、インサイドセールスで対応すれば解決するとも思えない。
営業担当Fさんが疑問を抱いた理由は、前期の訪問頻度増加と売り上げ低下の関連性やその要因について説明されていないからです。
また休眠顧客への対応では、インサイドセールスだけで何とかしようとしていると受け取られています。
インサイドセールスをタッチポイントとしたその後の営業プロセスを示されない限り、Fさんは疑念を持ちながら業務にあたることになるでしょう。
〈施策2〉
- 前期の課題
競合他社の価格競争により利益率が低下している - 今期の施策
新商品の開発と販売促進を強化する

Gさん
なぜ価格競争による利益率低下の対策が販売促進強化?
新商品を開発すれば本当に価格競争から脱却できるの?
利益率低下の要因や、競合他社の価格競争への対策についての具体的な説明が欠けています。
新商品の開発でそのような効果が得られるのか、販売促進強化とは具体的に何を指しているのかについて説明がないため、Gさんの頭には疑問だけが残ってしまいました。
このように抽象的で脈絡のない計画を示されても、メンバーが真の目的を共有し、精力的に取り組むことは難しいのではないでしょうか。
つまり、伝える側として重要なのは、確信のある結論を導くための前提や根拠を明示することです。
そして、その帰結を相手に伝えるためには、話を整理し、相手の理解を得る努力をすることが重要です。

話の飛びをなくすためには「したがって」「つまり」「このように」という言葉を意識すると良いです。
話の間にこれらの言葉を入れてみて結論と根拠、その方法がすんなりとつながるか確認してみましょう。
「Why5回」と「So What?/Why So?」
問題の解決には、「Whyを5回繰り返しなさい」「So What?/Why So?と問いながら解決策を考えなさい」などと言われた経験はありませんか?
前者は問題の表面的な原因ではなく、深層的な原因を探ることためのテクニックです。
後者は自分の思考を深め、根拠を明確にし、論理的な筋道を作るというように伝える相手を意識したものです。
Why5回
Why(なぜ)を5回繰り返すことで、仮説の立案とその検証を繰り返し、本質的な課題を抽出することが出来ます。
例えば「売上が落ちている」という課題に対して、上司から「新規顧客の獲得にもっと力を入れろ」というだけの指示があった場合、あなたはどのように感じるでしょうか。
「既存顧客だけでスケジュールが埋まっている」
「新規顧客を獲得しても大した売上にならない」
こんな声が営業担当者から聞こえてきそうです。そんな状態で上手くいかないことは、誰の目にも明らかでしょう。
こんな時、Whyを5回繰り返して課題を深堀してみると、見出された解決策は納得感のあるものになります。
[課題「売上が落ちている」ことに対するWhy]
Why?なぜ?
※上記の例ではここで止まっている。さらにWhy?を繰り返す。
Why?なぜ?
Why?なぜ?
Why?なぜ?
この例では、自社の状況や新規顧客開拓の重要性や営業戦略が伝わっていない事による、営業担当者のモチベーション低下が原因でした。
今の主要顧客もはじめは新規顧客だったはずです。
例えば、新規顧客の売上がはじめは少なくとも、将来的に主要顧客に育て長期的な関係を築くLTV(顧客生涯価値)の視点で考えることで、新規顧客開拓に精力的に取り組むことに繋がります。
このように、深層の課題まで踏み込むことで、新たな解決策が見えてくることがあります。
So What?/Why So?
「So What?/Why So?」を簡単に説明します。
- So What?
情報を示し「つまりこういう事です」と、事実を要約したりルールや法則性を示す - Why So?
So Whatに対し、示した情報をもとに「なぜそれが言えるのか」を説明できる
この方法では、例えば自分の主張に対して、疑問に思う可能性がある点を予測しそれに対する答えを用意します。
また、それに対し、相手がなぜそうなるのかと突っ込んできそうなところの根拠を示します。
このようにして、自分の主張や提案が論理的で説得力のあるものであることを示すことができます。
ところで、「自分はよく“要するに”と言うから常にSo What?をしています」という方がいらっしゃいます。
でも、「上役から言われた事をそのまま伝えている」、「まとめた内容が正しくない」という場合は必ずしもそうとは言えず、「要するに」がただ口癖になってしまっているだけかもしれません。
あなたの「要するに」が本当に「So What?」か、上記に示した両者の関係性をいま一度確認してみてはいかがでしょうか。

ここでは、So What?/Why So?についてここでは基本的な考え方を理解していただく事を目的として簡単に説明しました。もっと詳しく知りたい方はロジカル・シンキングに関する様々な書籍で紹介されていますので、ぜひお読みいただければと思います。
最後に
本記事では、ロジカルな説明の重要性とその活用方法について述べました。
ロジカルな説明は、相手を納得させ、思い通りの反応を得るために必要です。
特に顧客や取引先、上司や部下などに何かを伝える際には、相手を説得するための筋の通った論理的な説明が求められます。
ロジカルな説明はコミュニケーションにおいて重要なスキルであり、プレゼンテーションや広告制作にも活かすことができます。相手を納得させ、思い通りの反応を得るためには、相手の課題や期待する反応を考慮し、結論や根拠、方法を明確に伝えることが大切です。
関連記事
【ロジカルシンキング①】ロジカルシンキングの基本をわかりやすく説明
こちらの記事もおすすめです

このお役立ち記事は、私がこれまでにお客様のプロモーション課題に取り組んできた経験や、お客様からお寄せいただいた質問をもとに執筆しています。印刷をデザインやマーケティングの観点も交えながら、読者の方に少しでも分かりやすくお伝えする事を心掛けています。