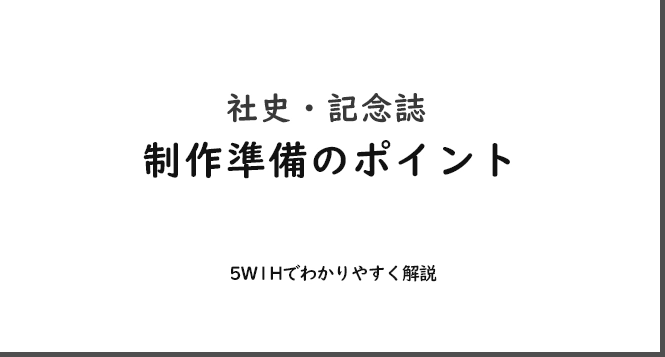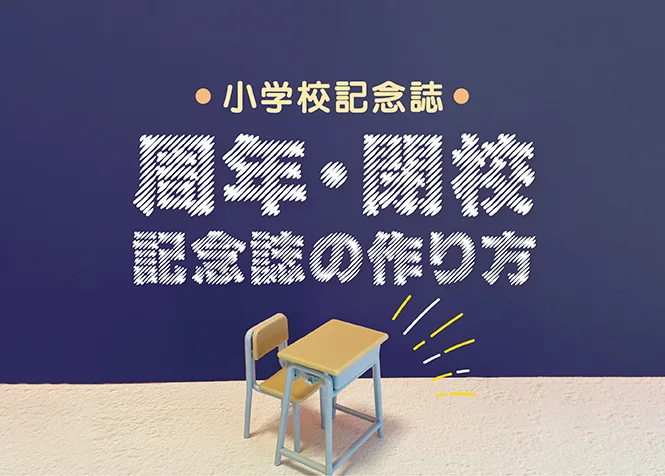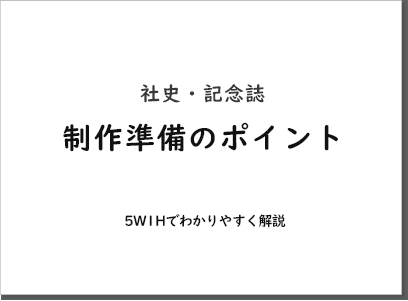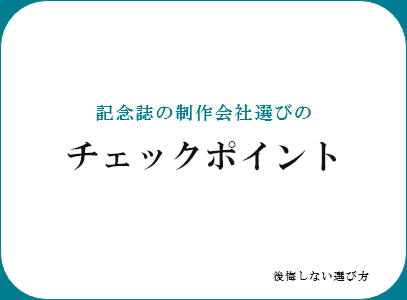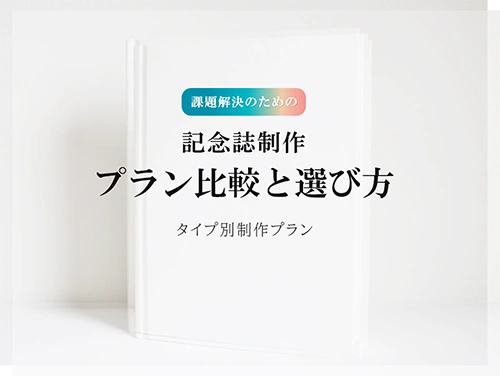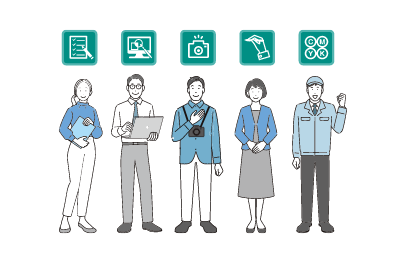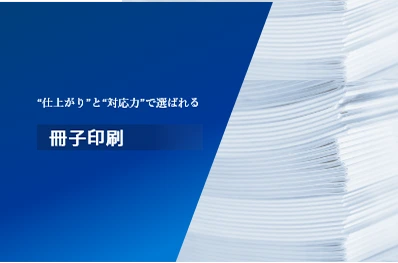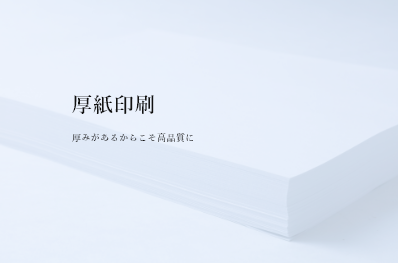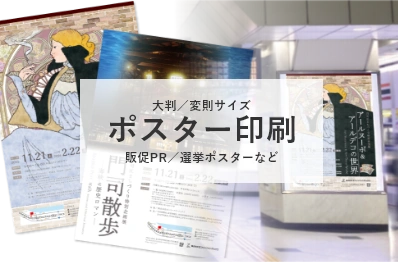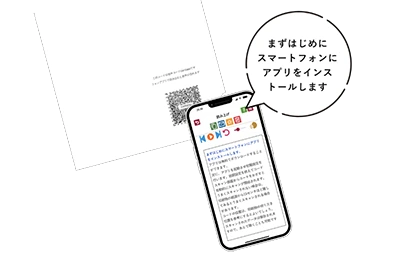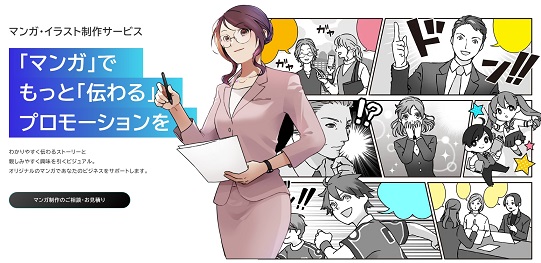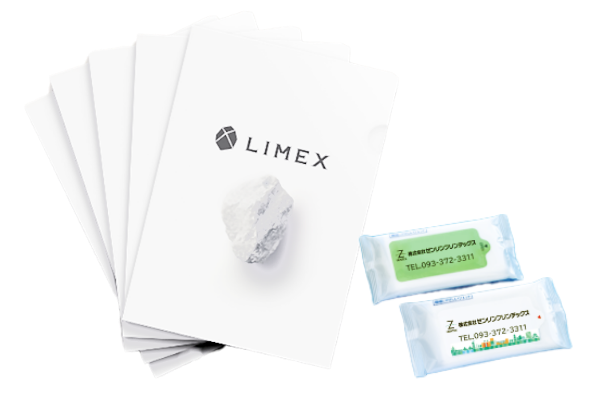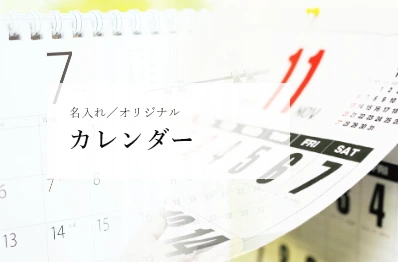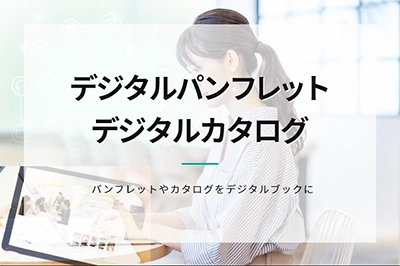創立記念や周年行事の節目で多くの企業・団体が制作する「社史」や「記念誌」。
その制作において、制作会社選びは非常に重要です。
パートナーとなる制作会社を探す際は、インターネットで検索、いつも発注している制作会社に相談するなどの手段がありますが、事前にそれぞれの特徴を理解し、準備をしっかり行っておくことが必要となります。
本記事を参考にして、あなたにとって最適な制作会社を見つけて出してください。

本サイトは、株式会社ゼンリンプリンテックスが制作・運営しています。
本記事は、ゼンリンプリンテックスの、社史・記念誌制作のノウハウ・経験をもとに執筆しました。
社史、記念誌の基本が知りたい方はこちらがおすすめです。
社史・記念誌の制作会社を見つける方法 5選
社史・記念誌を制作する会社を見つける代表的な方法を5つ紹介します。
1.オウンドメディア・お役立ち系の記事からさがす(おすすめ)
オウンドメディアとは、トリプルメディア(ペイド・アーンド・オウンド)のひとつに分類されるマーケティング手法です。
自社が保有・運営する「ブログ」や「情報発信サイト」などを指します。
広義でコーポレートサイトなどを含む場合がありますが、ここでは情報発信系サイトに限定しています。
メリット
インターネットで「記念誌 作り方」「社史 制作費用」などのキーワードで検索すると、制作会社が知見をまとめた記事が表示されます。
「記念誌 作り方」は、情報収集型(Know)クエリと呼ばれ、制作の流れや準備に関する情報を得るために使われる検索ワードです。一方「社史 制作費用」は、依頼先の候補を探す際に使用される検索ワードで、行動・取引型(Do)クエリなどと呼ばれます
このように、複数の検索意図に対して網羅的に記事を公開している会社は、知見や経験が豊富である可能性が高いといえます。
このようなオウンドメディアの記事は、自社のノウハウや経験をベースにすることが多いため、その会社の考え方や得意分野が見えてきます。記事を読んで「信頼できそう」と感じたら、そのサイトから相談や問い合わせが行えるのも特徴です。
注意点
このようなメディアでは外注のSEOライターに記事執筆を委託している場合があります。一部の記事は、検索で上位表示させるという視点だけで作成され、オリジナリティが無いものもあるようです。
そのような場合は、自社のノウハウや知見を示すものとは言えませんので注意が必要です。
記事の内容を参考にしつつも、実際にその会社の担当者の話を聞いてみることが肝要です。

今お読みいただいているこの記事も、ゼンリンプリンテックスが運営するオウンドメディアの記事です。社史・記念誌制作に役立つ情報を随時発信していますので、ぜひ他の記事もご覧ください。
2.印刷会社や出版社のサービスページ(サイト)からさがす
社史や記念誌の制作は印刷会社や出版社がサービスとして提供しています。会社の公式サイトに「社史制作」「記念誌作成」といったページを設けサービス内容を紹介していることが一般的です。
メリット
サービスページでは、その会社の制作サービスについて説明されているため、会社ごとにページを見比べることで、自社に合いそうな会社を絞り込めます。また、問い合わせフォームや資料請求が準備されている場合は、すぐに相談など次のステップへ進むことができるため便利です。
注意点
掲載されている情報は「会社が見せたい部分」「言いたい事」に偏っている場合があります。やはり、実際の体制や対応力は、打ち合わせで確認する必要があります。

ゼンリンプリンテックスでも、社史・記念誌制作のサービスページをご用意しています。
3.比較サイトを利用する
制作会社を一覧で探せる「比較サイト」を活用する方法もあります。
メリット
複数の会社を一覧で確認できるため、効率的に候補を集められますし、サイトによっては資料一括請求や問い合わせフォームが整備されています。
注意点
ただし、社史・記念誌は、他の印刷物と大きく異なるノウハウが要求され、価格だけで選んでしまうと後悔する場合も少なくありません。そのような中で、比較サイトでは価格重視の案件が集まることが多いサイトもあり、制作会社もそのつもりで安価な見積もりを提示することから、後々のトラブルにつながりことが懸念されます。
また、掲載順や評価が「広告枠」「掲載料」に依存している場合もあり、必ずしも客観的なランキングとは限らない事にも留意したいものです。
こちらも、最終的には公式サイトを確認し、打ち合わせで実際の対応力を見極めることが必要です。
【比較サイトの例】 BOATER(ボーター)
ボーターは、業務のアウトソーシングの業務ノウハウやサービス資料が検索できる、外注先の比較サイトです。
社史・記念誌の制作会社のおすすめ15社を紹介するなど、適切なパートナーを見つけるために役立つコンテンツを提供しています。
4.いつもの制作会社(印刷会社など)に相談する
普段から取引のある印刷会社や広告代理店、デザイン会社に社史・記念誌制作を相談する方法です。日頃の付き合いがある相手なので、依頼しやすく、安心感もあります。
メリット
自社の事業内容や文化をある程度理解してくれていることが多いでしょう。既存の信頼関係があるため、やり取りがスムーズな傾向があります。
注意点
社史・記念誌のような専門性が高い制作物は、経験や実績が不足している可能性があります。知識やノウハウが不足している場合、ただのパンフレットのようなものになってしまいかねません。また、そのような会社は、企画や編集部分を外注するケースもあり、結果的にコストが高くなることもあります。
「付き合いがあるから」という理由だけで決めてしまうと、期待していた仕上がりにならない場合がありますので、注意が必要です。
5.取引先や知人から紹介してもらう
営業活動において、テレアポや飛び込みに比べて紹介営業は非常に効果の高い手法とされています。
その理由のひとつは、紹介者との信頼関係がすでに築かれている点にあります。
社史・記念誌の制作会社を探す際も、「きちんと作れる会社」という前提で紹介されるため、有力な選択肢のひとつになり得ます。
メリット
紹介者が実際に取引した経験をもとに推薦してくれるため、対応力や品質などの客観的な情報が得られます。
また、自分で一から探すよりも選定にかかる時間を短縮できます。
注意点
「良い会社」として紹介されても、自分のニーズに合っているとは限りません。
紹介を受ける際は、「なぜその会社を勧めるのか」を具体的に聞き、自社に合っているかを検討するようにします。
もちろん、実際に制作会社と話をすることも重要です。その際は、次項で説明する「準備しておきたいこと」を参考にしてください。
準備しておきたいこと-
自社にとって最適な制作会社を探すために
制作会社に「何を依頼するか」具体的に考える
社史や記念誌を制作する際には、「自社で対応すること」と「制作会社に依頼すること」を明確にしておく必要があります。
資料整理や原稿作成なども制作会社に任せると安心ですが、もちろんその分コストが膨んでしまいます。その結果、想定以上の見積額に驚くことが少なくないようです。
そこで、自社でできることはできるだけ社内で対応し、難しい部分だけをプロに依頼するという視点も持つようにすると良いでしょう。
例えば、
- 自社で対応すること
原稿作成、資料や写真の整理など - 制作会社に任せること
デザイン制作、印刷やその手配、インタビュー記事の執筆
このように、自社で原稿作成を行うとなると、「原稿を自分たちで書けるか不安」という声もよく聞かれますが、私どもの経験上、制作会社が適切なアドバイスやチェックを行えば、十分に対応できるケースが多いようです。
とは言っても、どこまでが社内で対応可能でどこからをプロに任せるべきかを判断することは、経験がないと難しいかもしれません。また、制作会社によってサポート内容は異なりますので、まずは気になる制作会社に相談し、サポートの範囲・内容を確認することをおすすめします。
これは制作会社に依頼がおすすめ!
- 企画・編集
企画案、冊子構成、インタビュー取材・撮影、記事作成など、魅力的な誌面をつくるためには、ノウハウや経験がものを言います。また、社史・記念誌はページ数が多く関係者も多いため、スケジュール調整や校正の取りまとめをプロに任せると社内負担を軽減できます。 - デザイン・レイアウト
開きたくなる表紙、読みやすい誌面、デザイン・レイアウトの工夫で「残したくなる1冊」に仕上げる技術が必要です。 - 印刷・製本のノウハウ
後世に残すものとしてふさわしい装丁や仕様の提案、最適な印刷品質で仕上げてもらえます。
その他、考えておきたいこと
他の印刷物の制作と同様、事前に制作の目的などをまとめておくことも忘れてはいけません。
- 社史・記念誌を発行する目的
- 誰に何を伝えるか?ターゲット設定する
- 掲載する内容やデザインの方向性、完成イメージ
- 発行時期とスケジュールの決定
- 配付する場面、配付部数を想定する
これらについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
記入しながら整理する!
「制作準備 ワークブック」を無料ダウンロード
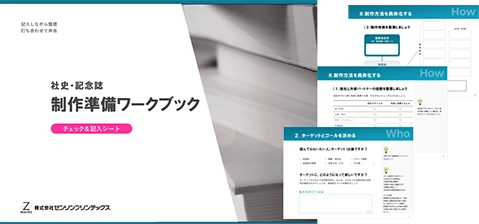
「わかりやすい」と好評の資料を無料でご提供中
はじめに押さえておきたいポイントを記入しながら整理!社内会議や外部パートナーとの打ち合わせにも便利です。
社史・記念誌制作会社を選ぶ際のポイント
社史や記念誌は他の印刷物と異なるノウハウや経験が必要とされるため、近くに適当な制作会社がないという状況はよくあることです。
距離的制約をどう捉えるか
昨今は、商談やミーティング、データの受け渡し、制作物のチェック・校正などを、オンラインでも行えるようになりました。
そのため、制作会社を選ぶ際に以前ほど地域にこだわる必要はなくなりました。
しかしそれでも、対面での打ち合わせが必要な場合や、資料整理から依頼する場合などには、距離的問題はひとつのハードルになるでしょう。
この距離的不利が制作に影響を及ぼす場合でも、「任せてくれ」という制作会社よりも、きちんとそのことを説明してくれる、
もしくは、どのようなものをどのように作るのかを考えて、そのうえで判断してくれる制作会社を選ぶべきでしょう。
制作会社の選び方がもっとわかる記事
社史、記念誌の制作会社の選び方を詳しく説明した記事がありますので、ぜひご覧ください。
FAQ—社史・記念誌の制作会社さがしでよくある質問
社史・記念誌に関するご質問の中から、制作会社に関するものをいくつか紹介します。
制作会社なら、どの会社でも社史や記念誌記念誌を制作できるとは限らないことに留意してください。
例えば、いつもデザインをお願いしている制作会社や、ネット検索で表示された近場の制作会社が、必ずしもあなたの希望通りのものを制作できるとは限りません。
制作会社がイメージするものとあなたがイメージしているものが大きくかけ離れていると、後々トラブルにつながる可能性があります。まずは、前項「自社にあった制作会社を探すために準備しておきたいこと」を準備したり、参考にしたい他社見本などを示し、具体的なイメージを伝えるようにしてください。
もちろん、一般的なデザイン会社であれば、“冊子”としてのデザインは可能です。しかし、もしあなたが社史や記念誌としてのアドバイスを望むのであれば、それに適切に応えることが難しいかもしれないということも、念頭に置いておくとよいでしょう。
運営サイトが調査を行い閲覧する人にとって有益な情報を掲載しているはずですので、目安のひとつにはなります。しかしながら、必ずしも、掲載されている会社のサービス内容が自社に合っているとは限りません。
気になった会社のサービスページを実際にご自身で確認されること、わからないことは問い合わせることを強くおすすめします。
さいごに
社史・記念誌は、企業・団体の歴史と未来を繋ぐ大切な架け橋となる存在であり、単なるパンフレットでも冊子でもありません。
あなたが納得のいく社史・記念誌をつくりたいなら、そのことを真に理解している制作会社をパートナーとして選ぶことをおすすめします。
自社に合った制作会社を選び、連携を密にし、ぜひ理想の一冊を創り上げましょう。
社史や記念誌ならゼンリンプリンテックスにお任せください
社史・記念誌の制作は、ノウハウと経験が必要です。また、社史・記念誌の印刷には高い品質が求められます。
ゼンリンプリンテックスは、企画・制作から印刷まで、お客様の社史・記念誌づくりを全力で支援いたします。
ご予算などご状況に合わせてご提案も可能です。お気軽にご相談ください。
| 社名 | 株式会社ゼンリンプリンテックス |
| URL | https://zpx.co.jp/ |
| 設立 | 1947年 9月 |
| 事業所 | 東京、福岡、熊本 |
| 関係会社 | 株式会社ゼンリン、株式会社ゼンリンデータコム、株式会社ジオ技術研究所など 関係会社一覧 |
関連記事

【特集記事】広報・販促・宣伝をサポートするパートナー
選ばれる5つの理由
「デザイン」「印刷」「デジタルコンテンツ」の依頼先をご検討中ですか?
ゼンリンプリンテックスがお客様に選ばれている理由を特集記事にまとめました。